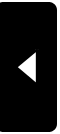2013年02月08日
冬のオイカワ
冬になるとオイカワ、どこ行っちゃうの?
そんな「オイカワのなぞ」について考えてみたいと思います。
そんな「オイカワのなぞ」について考えてみたいと思います。
まずご覧頂きたいのは、
やまべ釣振興委員会さんの解説です。
やまべ釣振興委員会さんは、
オイカワの競技エサ釣りをしている方たち。
オイカワ釣りの達人たちです。
一時間に100匹以上釣ってしまうそうです。
そんな猛者たちの解説です。
以下、「ヤマベ釣り・時速100尾への招待状」から抜粋です。
寒い時期のポイント-
気温も水温も下がる1~3月、この時期は大変難しい。
ヤマベは越冬体制で、代謝を低くするためにほとんど動かない。
それでも、目の前にエサがあると、あまり動かずに食べようとする(いわゆる「居食い」)。
また、晴れて気温が上がると、近くまでなら動いて就餌する。
では、どこで越冬しているか。
深いトロ場、外敵に襲われずにすむようなテトラの中や、暖かい流れの支流筋…あまり多くはない。
水深数メートルのトロ場で越冬している場合は、我々はお手上げ。大河川はそういう所が多い。
小河川だと、そんな深場はないから、テトラ周りや、ピーヤ(橋桁)周り、護岸近くの深場などが狙い目。
晴れて暖かい日は、もっとポイントは広がる。支流の吐き出し近くも候補だ。
しかし、あまり寒い時は、こちらの体もこたえるので、釣りは休みましょう(^_^;)
やまぺ釣振興委員会さんの解説では、
冬の間は、活性が落ちて、
障害物に隠れたり、底に沈んでいるとのこと。
僕も、冬場は、活性が落ちて、あまり動かなくなると考えています。
それは、他の魚にも言えることで、
僕が水槽で買っているタナゴなども、
冬になって、あまり動かなくなっています。
ブラックバスも、同じような性質があると言われています。
また、活性の落ちた魚が、障害物や深場にとどまるというのも、
他の魚にもいえることで、
これもまた、うちの水槽でも確認されます。
水温については、とても難しい要因だと思います。
一般的に水温が下がって、活性が落ちるということになりますが、
一概にそうとも言えないということがあります。
それは、水温が低くても釣れることがあるからです。
水温だけ比較すれば、
柳瀬川も、黒目川も、そんなに変わらない。(以前、siroyamasakuraさんが調べてました)
むしろ、柳瀬川下流は、黒目川よりも高いです。
でも、黒目川のほうが圧倒的に釣れるのはなぜでしょう。
また、柳瀬川の上流と下流を比較しても、
下流の方が、温かいのに、
釣果はほとんど変わりません。(両方釣れない。。。)
単純に、水温が高ければ釣れるということではないのだと思います。
私の経験では、
越辺川の上流から中流付近で、
真冬に爆釣したことがあります。
かといって、少し暖かくなってから、同じポイントにいっても
まったく反応がなかったということがありました。
このような過去の経験から、
水温だけでなく、
なんらかの要因で、
活性が上がったり、下がったりしているのだと思います。
その要因が何なのか。。。。
最近、考えていたのは、水草の影響。
黒目川において、オイカワが付いている場所は、
明らかに水草周りでした。
これは、やまべ釣振興委員会さんの、
障害物についている説とも一致します。
なぜ、水草に付くか。
それは、水流が穏やかになり、体力を使わなくてすむから。
身を隠して、安全に過ごせるから。
水草につく、有機物などを餌とできるからなどが考えられます。
かといって、水草があれば、オイカワが釣れるかといえば、
そうではありません。
先日の柳瀬川では、水草周りでオイカワの反応がありませんでした。
このことから、水草も絶対条件ではなく、
一要因に過ぎないといえます。
そのほかに、考えられる要因としては、
水質。
国土交通省の水文水質データベースをみてみると、
冬の時期には、おおむね、
透明度が上がる
B0Dが下がる(水が綺麗になる)
ようです。
これらのことは、オイカワの釣れない時期と一致しています。
このような水質の変化は、
オイカワだけでなく、
オイカワが餌としている
微生物などにも影響していると思われます。
それもオイカワの活性に関係あるかもしれません。
まだ他にも
水量
気温
時間
寒暖差
風
天気
などなど
様々な要因が考えられます。
以上、いろいろな可能性について、
述べてみましたが、
私の至った結論としては、
複合的な要因が、オイカワの釣果に関連しているのではないかということです。
なんだか、
的を得ない結論ですが、
これらを科学的に検証することは、
現在の私にはできていません。
まあ、これができたら、
もっとブログに釣果報告を書けているはずですが。
だから、釣りをして、釣りをして、釣りをして、、、、
なんども、なんども、
釣れても、釣れなくても、
川に行ってしまうのです。
オイカワの謎を解くために。
(あ~、これが仕事ならよかったのに(苦笑))
話がそれてしまいましたが、
できるかぎり正確に、
オイカワの生態を捉えるために、
調査を繰り返して行きたいと思っています。
長くなってしまったので、
今日はこの辺で。
Posted by sanche at 10:17│Comments(6)
│フライフィッシング
この記事へのコメント
おはようございます
先日はお疲れさまでした。
彼等が毛鉤で釣れるかどうかは、その時の捕食対象も関係すると思います。
ヒラタ類の生息状況やハッチの状況によるとも思いますし、雑食性であることから
動物性たんぱく質以外を「メインに」捕食している場合もあるでしょうし。
コイフライも同じですが、パンが多く撒かれている場所ではコイはみな上を向いていて、
あまり撒かれない場所では底の餌を主食にしています。
僕の仮説では、ヒントは啓蟄にあると思ってます。
・・・もうすぐですよ。
先日はお疲れさまでした。
彼等が毛鉤で釣れるかどうかは、その時の捕食対象も関係すると思います。
ヒラタ類の生息状況やハッチの状況によるとも思いますし、雑食性であることから
動物性たんぱく質以外を「メインに」捕食している場合もあるでしょうし。
コイフライも同じですが、パンが多く撒かれている場所ではコイはみな上を向いていて、
あまり撒かれない場所では底の餌を主食にしています。
僕の仮説では、ヒントは啓蟄にあると思ってます。
・・・もうすぐですよ。
Posted by siroyamasakura at 2013年02月09日 09:06
こんにちは、やまべ釣振興委員会の管理人、津里彦です。リンクありがとうございました。ヤマベの食性と季節について感じたことを少し。ヤマベは雑食性で、植物性の餌の方が楽に食べられるが、カロリーは低い。動物は捕るのにエネルギーは使うが、カロリーは高い。冬場は特に川虫がおらず、動物性のエサはほとんどないと思われます。川虫で釣っていた時期もかなり長いのですが、冬場はほとんど釣りになりませんでした。練り餌は植物性のエサなので、冬でもあまり動かずに採餌することができ、まずまず釣れる、と思います。フライは、冬場はかなりテクニックがいることと推察します。
冬の川で越冬する場所では、伏流水のあるセキ下などにも、群れを成して集まっていることがよくあります。伏流水の温度が相対的に高いからでしょうか。(茨城・山田川の例) 朝、-5℃以下の気温の時、魚はたくさんいるのに、エサが目の前に落ちても見向きもしないことがよくあります。少し日が上がって、1、2℃気温が上がると途端に食い始める、というパターンもよくあります。水温が低い状態でも、魚はいますので、水温上昇が採餌を促すと思われます。氷の下に越冬している群れもいますが、氷を割って釣りをするときも同じような傾向が見られます。そのような場所はかなり少なく、時にはそのポイントだけ爆釣、ということも多くあります。また、雨が降って水量が増えると、魚が広範囲に散って、ポイントが広がることもあります。
冬の川で越冬する場所では、伏流水のあるセキ下などにも、群れを成して集まっていることがよくあります。伏流水の温度が相対的に高いからでしょうか。(茨城・山田川の例) 朝、-5℃以下の気温の時、魚はたくさんいるのに、エサが目の前に落ちても見向きもしないことがよくあります。少し日が上がって、1、2℃気温が上がると途端に食い始める、というパターンもよくあります。水温が低い状態でも、魚はいますので、水温上昇が採餌を促すと思われます。氷の下に越冬している群れもいますが、氷を割って釣りをするときも同じような傾向が見られます。そのような場所はかなり少なく、時にはそのポイントだけ爆釣、ということも多くあります。また、雨が降って水量が増えると、魚が広範囲に散って、ポイントが広がることもあります。
Posted by 津里彦 at 2013年02月09日 18:39
siroyamasakuraさん
冬のオイカワが何を食べているのか。
とても重要なポイントですね。
虫を食べてなかったら、フライへの反応も悪くなる。
ありえますね!
今度、川虫も探してみようと思います。
でも、手が冷たくなりそうだな〜(>_<)
冬のオイカワが何を食べているのか。
とても重要なポイントですね。
虫を食べてなかったら、フライへの反応も悪くなる。
ありえますね!
今度、川虫も探してみようと思います。
でも、手が冷たくなりそうだな〜(>_<)
Posted by sanche at 2013年02月09日 19:46
at 2013年02月09日 19:46
 at 2013年02月09日 19:46
at 2013年02月09日 19:46津里彦さん
コメント&貴重な情報、ありがとうございます。
冬は、動物性より、植物性。
なるほど〜。
ヤマベ釣り・時速100尾への招待状にあった、
「居食い」とは、このようなことと関係あるのですね〜。
山田川では、氷が張っていても、
オイカワが釣れるということに、
まず驚きました。
水温、気温の関係。とても重要なのですね。
不思議がいっぱいです。
エサで釣ると、またいろいろなことが見えてきそうに思いました。
今度、チャレンジしてみます。
コメント&貴重な情報、ありがとうございます。
冬は、動物性より、植物性。
なるほど〜。
ヤマベ釣り・時速100尾への招待状にあった、
「居食い」とは、このようなことと関係あるのですね〜。
山田川では、氷が張っていても、
オイカワが釣れるということに、
まず驚きました。
水温、気温の関係。とても重要なのですね。
不思議がいっぱいです。
エサで釣ると、またいろいろなことが見えてきそうに思いました。
今度、チャレンジしてみます。
Posted by sanche at 2013年02月09日 20:01
at 2013年02月09日 20:01
 at 2013年02月09日 20:01
at 2013年02月09日 20:01 考えれば考えるほど、疑問が深まっていきます。
水温は大きな要因ですが、その中で上昇した時、下降した時。
水量が増えた減った。
気圧が下がった上がった。
考えるときりがありません。
どうしてだろうと考えることと、データを集めることにより方向が見えてくるような気がします。
今後とも宜しくお願いします。
水温は大きな要因ですが、その中で上昇した時、下降した時。
水量が増えた減った。
気圧が下がった上がった。
考えるときりがありません。
どうしてだろうと考えることと、データを集めることにより方向が見えてくるような気がします。
今後とも宜しくお願いします。
Posted by jetpapa at 2013年02月11日 21:18
jetpapaさん
どうも仮説ばかり述べ立ててしまいました。
まだまだデータが足りないので、
たくさん釣りに行って、冬のオイカワの特徴を掴んでいきたいと
思っています。
明日も行っちゃうぞ−!
どうも仮説ばかり述べ立ててしまいました。
まだまだデータが足りないので、
たくさん釣りに行って、冬のオイカワの特徴を掴んでいきたいと
思っています。
明日も行っちゃうぞ−!
Posted by sanche at 2013年02月13日 01:06
at 2013年02月13日 01:06
 at 2013年02月13日 01:06
at 2013年02月13日 01:06※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。